9月に書いた翻訳ミステリーの頃より、ひたすら本を読んでいる。
ざっくりと近年(じゃないのもあるけど)のミステリを探して、以下を読んだ。タイトルの後ろにあるのが原題と発行年。邦題が原題と違う物は記した。原題通りだとピンとこなかったりして、邦題を考えるんだろうな。
シンデレラの罠 Piège pour Cendrillon 1962年
セバスチアン・ジャプリゾ 平岡 敦/訳 2012年 創元推理文庫
すごいね、作家の発想が。「わたしは探偵で 犯人で 被害者で 証人」
第四の扉 La Quatrième porte 1987年
ポール・アルテ 平岡 敦/訳 2002年 早川書房
次々起きる事件に一気に読んだ。第三部の幕間を読むと肩透かしで気が萎えたが、その後のひねり方に納得! そうくるか。トリックのひとつには「いや、痕跡残るだろ」と気にはかかったが。
悪魔のヴァイオリン Les violons du diable 2004年
ジュール・グラッセ 野口雄司/訳 2006年 早川書房
さらりと読めた。ちょっと物足りない。
欲望通りにすむ女(文庫)Passage du Désir 2004年
ドミニク・シルヴァン 中原毅志/訳 2007年 小学館
原題は「欲望通り」
殺人事件の容疑者を巡って、元警視のローラとマッサージ師のイングリッド、女性ふたりがバディとなって解決に挑む。様々なエピソードが挟まれるが、なんだろう、あんまり印象に残らなかった。イングリッドとローラシリーズの1作目となっている。
黒い睡蓮(文庫)Nymphéas noirs 2011年
ミシェル・ビュッシ 平岡 敦 /訳 2017年 集英社
えっ、その構成は反則ギリギリでは? とは思った。まあ私は印象派は好みじゃないし(笑)
恐るべき太陽(文庫)Au soleil redouté 2020年
ミシェル・ビュッシ 平岡 敦 /訳 2023年 集英社
クリスティー『そして誰もいなくなった』への挑戦、とあったので期待したが、ちょいと残念。
パリ警視庁迷宮捜査班 Poulets grillés 2015年
ソフィー・エナフ 山本知子・ 川口明百美/訳 2019年 早川書房
原題は「グリル・チキン」
群像劇なので、何度も人物名を確かめてしまう。それぞれ個性はあるんだけど。話的には面白く読めた。シリーズの1作目。
ずっとあなたを見ている(文庫)Fidèle au poste 2017年 自費出版から
アメリー・アントワーヌ/浦崎直樹 扶桑社
原題は「仕事に忠実」かな?
ロマンス? と思ったら、サスペンスに切り替わる。序盤を読んで邦題を「ああ」と思ったが、途中から「ああ!」になった。女は怖いね。
悪なき殺人(文庫)Seules les bêtes 2017年
コラン・ニエル 田中 裕子 /訳 2023年 新潮社
原題は「動物たちだけ」
孤独を抱えた人々。偽りの対象であっても、それを慈しむ。恐いが、染みる。
パリのアパルトマン(文庫)Un appartement à Paris 2017年
ギヨーム・ミュッソ 吉田恒雄 /訳 2019年 集英社
不動産屋の手違いで、ひとつのアパルトマンに借り手がふたり、男と女。ロマンス? と思いきや、違った。天才画家の遺作を探すふたりは、過去の事件を追いかける。キャラクターがね、イマイチ共感できないんだよな。
夜と少女(文庫)La Jeune Fille et la Nuit 2018年
ギヨーム・ミュッソ 吉田恒雄 /訳 2021年 集英社
青春の日の過ちが、今、陽の下に現れようとしている。男たちは犯罪の隠蔽をどうするのか。入り組んだプロットで、一気に読んでしまった。面白い。
死者の国 La Terre des morts 2018年
ジャン=クリストフ・グランジェ 高野 優 /監訳, 伊禮 規与美 /訳 2019年 早川書房
この本だけは序盤で読むのをやめた。グロテスクな表現は苦手なんだ。
念入りに殺された男 Son autre mort 2019年
エルザ・マルポ 加藤かおり/訳 2020年 早川書房
原題は「彼のもうひとつの死」
性暴力から逃れるために男を殺した女。自分の人生から死者を遠く離すために、もうひとりの女を演じ始める。なかなかのサスペンス。指紋のトリックは結果に不自然さを感じるが、大胆すぎる主人公の行動に目が離せなかった。
フランス・ミステリーの歴史で、古典が気になったので読んでみた。なお私はルパンもホームズも読んだ事がなかった。小学生の頃に児童書としてそれらの本があったが、いかにも「子供向け」な表紙に、ませた女児はそれらを手にする事はしないのだ。
もちろん、下記の本は児童書ではない。
バスティーユの悪魔 Les Amours d'une empoisonneuse 1863年
エミール・ガボリオ 佐藤絵里/訳 2020年 論創社
原題は「毒殺者の恋」
訳者あとがきによれば、著者の健康問題により中途で終わってしまった作品らしい。だからちょっと物足りなく終わるが、一応の解決はある。バスティーユからの脱獄計画のくだりなんて、デュマの『モンテクリスト伯』を思わせる(そしてそこからマンガ『銀色の髪の亜里沙』和田慎二も思い出しちゃうんだよね。『スケバン刑事』でも少年院からの脱獄あったな)。
ルルージュ事件 L'Affaire Lerouge 1866年
エミール・ガボリオ 太田浩一/訳 2008年 国書刊行会
世界初の長編ミステリーというので読んだが、読みやすく、面白い! 長いが、気にならない。身分という属性が人の人生を左右する時代。
鉄仮面 上・下(文庫)Les deux merles de m. de Saint-Mars 1878年
ボアゴベ 長島良三/訳 2002年 講談社
原題は「サン=マルス氏の二羽の鶇」
これも読んでおこうと。小説は長いが、流れる話も長い。1669年ピネローロ監獄から1703年バスティーユまで収監されていた実在の人物、マスクで顔を覆われていた謎の囚人(現在でも正体は不明)をモデルにした創作。飽く事なき情熱で、囚人を脱獄させようと奮闘する女と従者たち。
ファントマ Fantômas 1911年
ピエール・スヴェストル マルセル・アラン 赤塚敬子/訳 2017年 風濤社
ファントマに好感が持てなかったな。
怪盗紳士ルパン(文庫)Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur 1905-1907年
モーリス・ルブラン 平岡 敦/訳 2005年 早川書房
奇岩城(文庫)L'Aiguille creuse 1909年
モーリス・ルブラン 平岡 敦/訳 2006年 早川書房
原題は「空洞の針」
カリオストロ伯爵夫人(文庫)La Comtesse de Cagliostro 1924年
モーリス・ルブラン 平岡 敦/訳 2005年 早川書房
カリオストロの復讐(文庫)La Cagliostro se venge 1935年
モーリス・ルブラン 井上 勇/訳 1973年 東京創元社
ルパン物は、ミステリーというより冒険小説っぽい。面白く読めたけど。カリオストロ伯爵夫人の妖艶さに惹かれて復讐の方も読んだが、彼女が出て来ずに残念。
絶版殺人事件 Le Testament de Basil Crookes 1930年
ピエール・ヴェリー 佐藤絵里/訳 2019年 論創社
原題は「バジル・クルックスの遺言」
サンタクロース殺人事件 L'Assassinat du père Noël 1934年
ピエール・ヴェリー 村上光彦/訳 2019年 晶文社
絶版殺人事件を先に読んだ。皮肉な結末だが、なかなか良かったので、もう1冊。でもサンタクロースのトリックは、バレないか?
メグレと深夜の十字路 La Nuit du carrefour 1931年
ジョルジュ・シムノン 長島良三/訳 1979年 河出書房新社
メグレと若い女の死(文庫)Maigret et la jeune morte 1954年
ジョルジュ・シムノン 平岡 敦/訳 2023年 早川書房
メグレ物も初めて読んだ。若い女の死を先に読み、面白かったのでもう1冊読んだ。だが容疑者を17時間の尋問とか、そのうち5時間は立たせたままとか、戦前の日本かよ!(戦後も似たようなものかもね)とメグレに腹が立った。被疑者への虐待やん。フランスって人権にうるさいはずでは? それとも警察はどこもそんなもんなのか? という不快な感情のまま読んだ。
世界文学全集 26 ポオ ボオドレール集
1960年 筑摩書房
世界文学全集 21 ゴリオ爺さん 1835年
バルザック 高山鉄男/訳 1978年 集英社
久しぶりにポーを読む。こんなに読みにくかったっけ? 訳が古いせい? ついでに時代的にバルザックも読んでみた。
古典作品を連続で読んでいると、頭の中に馬車が走る。時代の空気感が脳に広がる。ずいぶん読んだな。
19世紀の性風俗も知りたくなって読んだ。とても興味深く、面白い。著者に興味がわいたのもあり、読んだ「悪女入門」、これもいい。フランス文学作品を元に解説している。エスプリの効いた文章に、くすくす笑う。若い女性は、ぜひ読まれるといい。男性も騙されないために読むといいかもね。
ファム・ファタルは単なる悪女ではなく、男を破滅させてこその存在、だそうだ。なおこれの男性版にオム・ファタルの単語がある。これは知らなかったな。
パリ、娼婦の館
鹿島 茂 角川学芸出版
パリが愛した娼婦
鹿島 茂 角川学芸出版
悪女入門 ファム・ファタル恋愛論
鹿島 茂 講談社
私が中学生だったか高校生の時だったか、日本の小説(何だったか忘れた)の中に出てきた単語の意味がわからずに、授業終了後に社会科教諭に質問した。
「先生、『青線』ってなんですか? この本に出てきたんですが。赤線は知ってますけど」
教師は正しく教えてくれた。ありがとう。
追記:
19世紀の作品を読むに、当時の政治状況が様々に影響しているので、フランスの歴史をWikipediaなんぞを読んだり、その関連も調べたりもした。
あのフランス革命から、第一共和政 → 第一帝政 → 復古王政 → 7月王政 → 第二共和政 → 第二帝政 → 第三共和政 と、政治の揺り戻しがすごい。怒涛の時代ね。
新版 馬車が買いたい!
鹿島 茂 白水社
すごく、興味深く面白かった。馬車については漠然としたイメージしかなかったけど、こんなにも種類があって、用途が違ったのね。馬車を自分で持つ事は、現代では高級車を所有するよりも更に大いなるステイタスだったわけだ。
そして馬車の呼び名は現代では車へと受け継がれていたりする。キャブリオレとかクーペとか。2頭の馬を一列に並べて引かせるのはタンデムで、バイクのタンデム(2人乗り)って、ここからか!

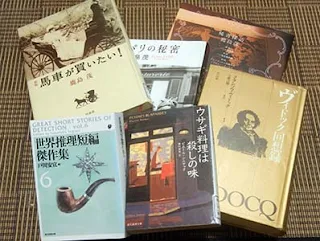














0 件のコメント:
コメントを投稿